認知症の介護に向き合う毎日。ご家族がどのような気持ちで日々を過ごしているのかを考えると、その大変さや不安は計り知れません。
特に、認知症に伴って現れる「周辺症状」(BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)は、多くの介護者にとって大きな課題です。
この記事では、認知症とその周辺症状について分かりやすく解説し、適切な対処法について考えていきます。
認知症とは
認知症は脳の神経細胞が徐々に壊れ、その結果、記憶や判断力、思考力などの認知機能が低下していく病気です。
原因にはアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症、血管性認知症などさまざまな種類があります。
それぞれ進行の仕方や症状は異なりますが、共通して日常生活に大きな影響を及ぼします。
周辺症状(BPSD)とは
認知症の症状は大きく分けて「中核症状」と「周辺症状」に分かれます。
中核症状は記憶障害や判断力の低下といった認知機能そのものの障害を指し、病気が進行するにつれて必ず現れる症状です。
一方、周辺症状(BPSD)は行動や心理状態に現れる症状で、必ずしも全ての人に起こるわけではありませんが、非常に多くの患者に見られます。
これらの症状は、介護者にとって負担が大きく、適切な理解と対応が求められます。
代表的な周辺症状
- 幻覚・妄想(誰かが自分のものを盗んだと思い込む)
- 徘徊(理由なく家を出てしまう)
- 興奮・攻撃性(突然怒り出したり暴力的になる)
- 抑うつ・不安(極端に悲しんだり、不安を訴える)
- 睡眠障害(夜中に目が覚めてしまう)
なぜ起こるのか?
周辺症状が起こる原因はさまざまで、脳の変化に加え、環境や身体の状態、心理的な要因が複雑に絡み合っています。
- 身体的要因:痛みや便秘、脱水などの身体的な不調
- 心理的要因:不安、孤独、混乱
- 環境要因:慣れない場所や騒音、照明の明るさ
周辺症状への対処方法
- 環境を整える
- 静かな場所で過ごしてもらう
- 適切な照明や温度にする
- コミュニケーションを大切に
- ゆっくりとした口調で話しかける
- 相手の気持ちに寄り添う姿勢を大切に
- 身体のケア
- 定期的な健康チェック
- 睡眠や栄養の管理
- 専門家への相談
- 介護支援専門員や医師に相談し、適切なケアプランを作成
介護者へのメッセージ
認知症の介護は孤独に感じることも多いかもしれません。
しかし、周りの支援や情報を活用しながら、少しずつ前向きに取り組むことが大切です。
自分自身のケアも忘れず、心の健康を守ってください。
まとめ
認知症の周辺症状は理解が難しく、対応に悩むことも多いですが、適切な対処法を知ることでその負担は軽減できます。
この記事が少しでも皆さんの支えになれば幸いです。

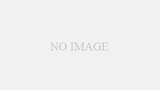
コメント