高齢化が進む中、「認知症」による「徘徊」は、多くの家庭で直面する深刻な課題の一つです。
突然姿が見えなくなった親を探し回る――そんな経験をしたご家族は少なくありません。
今回は、認知症の徘徊行動の原因や、事前にできる対策について分かりやすく解説します。
認知症の徘徊とは?
認知症の症状の一つとして現れる「徘徊」は、本人にとっては“目的のある行動”であることが多いのが特徴です。
たとえば、「家に帰る」と言って外に出たり、「仕事に行く」と言って昔の職場を目指したりします。
しかし、その目的地が分からずに迷子になったり、交通事故や事故に巻き込まれる危険性もあるため、早期の対策が重要です。
なぜ徘徊するのか?主な原因
- 時間・場所の認識の低下(認知機能低下)
自宅にいても「ここは自分の家じゃない」と思い込むことがあります。 - 過去の記憶との混乱
現在と過去の記憶が混ざり、「仕事に行かないと」「子どもを迎えに行かないと」と行動に移してしまうことも。 - 不安・ストレス
環境の変化や孤独感から不安になり、外に出て安心感を得ようとするケースもあります。
家族ができる「徘徊対策」
徘徊を完全に防ぐことは難しいかもしれませんが、事前の対策でリスクを大幅に減らすことが可能です。
1. GPS機器や見守りサービスを活用する
高齢者向けのGPS付きの見守り端末や、靴に装着できる位置情報発信機などを使うことで、万が一の際にも居場所を特定しやすくなります。
2. 玄関や勝手口に工夫をする
チャイムやドアロックの設置、「外出は◯時まで」といった視覚的なメッセージを貼ることも有効です。
3. 日常の会話や環境整備で安心感を与える
「大丈夫だよ」「ここがあなたの家だよ」と日々の会話で安心感を与え、心の混乱を減らしましょう。
落ち着ける部屋や安心できる人の写真を見える場所に置くのも良い工夫です。
4. 地域の見守り体制を利用する
「認知症高齢者SOSネットワーク」や「見守り協定」を結んでいる自治体では、行方不明時にすぐに情報提供を呼びかける体制があります。あらかじめ登録しておくことをおすすめします。
《登録方法》その自治体に住所のある認知症高齢者の方で徘徊の可能性がある方が対象です。
事前登録の申請は、ご本人の居住地の各区高齢介護課で行います。
まとめ:徘徊は責めずに、理解と備えを
認知症による徘徊は、決して“わがまま”や“困った行動”ではありません。
本人の不安や混乱が原因であることを理解し、責めることなく、見守りと対策を講じることが大切です。
「何かあってからでは遅い」と感じたときこそ、対策を始めるタイミング。
家族だけで抱え込まず、地域や専門家の力を借りながら、安心できる環境を整えていきましょう。

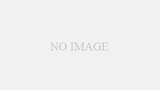
コメント